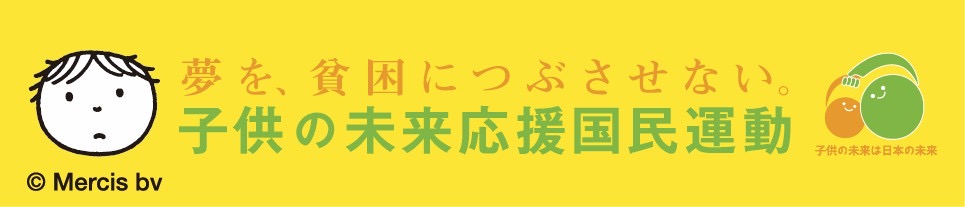みらいこども財団スタッフの大谷です☺️ 毎月、社会的養護や児童養護施設について、制度や暮らしなどをお伝えしています。
さてみなさんは「自立援助ホーム」をご存知ですか?
先日みらいこども財団ボランティアクルー向けの勉強会で、自立援助ホーム職員さんに講演をしていただきました。児童養護施設との違い、どのように子ども達は入居してくるのか、子ども達の生活、支援者として・普通の大人としてできることなど、学びになる内容を沢山お話いただきました。
この内容をもっと多くの人に知っていただきたい!と思い、講演の内容をもとにご紹介します。
ぜひ最後まで読んでいただければ嬉しいです。
はじめに 自立援助ホームとは
児童養護施設などで暮らす子どもたちの多くは、高校を卒業するとたった一人で自立をします。「18の壁」という言葉もあるように、親の支えなく一人で生きていくには大きな困難が伴います。
その困難な移行期間を支える受け皿の一つが「自立援助ホーム」。自立援助ホームは、衣食住だけでなく、若者たちが社会で生き抜くための実践的な力を身につける場となっています。
しかし自立援助ホームの役割はそれだけではありません。自立援助ホームの入所経路として最も多いのは「家庭から」。児童養護施設や里親家庭を経ず、15歳以降に直接家庭から入居する子が多くいます。そこにはどのような背景があるのでしょうか?またどのようにこうした若者の自立を支えるのでしょうか?
今回は自立援助ホーム職員さんの講演に基づき、4つの観点から、自立援助ホームについてご紹介します。
その1. 「児童養護施設を出た子のための場所」ではない。入居者の4割以上が「家庭」から
自立援助ホームは児童福祉法に基づき、“義務教育終了後、他の社会的養護の措置を解除された青少年 及び都道府県知事が認めた青少年に、自立のための援助及び生活指導を行う場所”とされています。
つまり、
他の社会的養護の措置を解除された青少年=児童養護施設や里親家庭から来た青少年
都道府県知事が認めた青少年=家庭などから来た青少年
となります。
このうち、全国自立援助ホーム協議会の調査によれば、入居経路として最も多いのは「家庭から」であり、その割合は43.3%にものぼります。これまで一度も児童養護施設や里親家庭などに入ったことがなく、家庭から直接入居してくる若者が最も多いのです。
なぜ、彼らは家庭を出てホームに来る必要があるのでしょうか。その背景には、深刻な家庭環境があります。
「精神疾患を持つ母親の世話を、幼い頃からずっと担ってきた」
「家庭内で性的な被害を受けたものの、母親に信じてもらえず堪えてきた」
など、こうした子ども達は、不適切な養育に長期間さらされ、より大きな心の傷を負っています。自立援助ホームは、見過ごされてきた家庭内の困難から逃れてきた若者にとっての最後の砦でもあります。
その2. 無償の住まいではない。家賃を払い、「世帯主」になる自立へのステップ
自立援助ホームは、若者を保護するだけでなく、社会の一員として生きるための実践的な仕組みが組み込まれています。この仕組みを「児童養護施設との主な違い」で見ていきます。
1. 契約による入居
児童養護施設への入居が行政による「措置」であるのに対し、自立援助ホームは本人の意思に基づく「契約」によって入居します。
つまり自分の意思で暮らしの場を選ぶことができます。
ただ、「ほかに行くところがないから」という切実な背景を抱えている子が多いということは一つ課題です。
2. 就労と寮費の支払い
講演していただいた職員様のホームでは、入居者は就労し、得た給料の中から寮費月3万円(高校生は半額)を納める形を取っています。これは、家賃を毎月支払うという社会生活の基本を学ぶための重要な仕組みです。
また、納められた寮費の一部は積み立てられ、退居する際の支援金として本人に還元されるという取り組みも行っているため、一人暮らしを始める際の資金にもなります。
※運営は各自立援助ホームによるところが大きく、就労を必須とせず、寮費を取らないホームもあるので、あくまで一例です。
昼間は学校・夕方や長期休みにアルバイトをする高校生、日中は勉強と部活・週末にまとめてバイトをする大学生、学校には通わず複数の仕事を掛け持ちする子、など入居する子どもはそれぞれの生活を送ります。
3. 一人一人が「世帯主」になる
最も特徴的なのが、入居者一人一人がホームの住所に住民票を移し、自分自身が「世帯主」になるという点です。
これにより、国民健康保険への加入手続きや、行政からの給付金などの通知の受け取りと申請などを、職員と一緒に自分で行うことになります。
自立後に必要な行政手続きを、ホームにいる間に具体的に経験できる貴重な機会となります。
その3. 「禁止する」のではなく「失敗を見守る」
講演者さんの自立援助ホームでは、「入居中は痛い目見てなんぼ」という考え方に基づき、支援をしています。法律に違反したり、生命に関わるような危険なことでない限り、大人が見て「危なっかしい」と感じる選択も、あえて「禁止しない」という方針を貫いているそうです。
その理由を、講演者さんはこう話してくださいました。
「禁止されたことは、おそらく退居してからやるからです。どうせやるなら入居中にやってもらった方が見守りもできるし、フォローできるからいいという考え方をしています。」
例えば、「コンセプトカフェで働きたい」と言い出した子がいました。労働契約が曖昧なことも多い業界のリスクは伝えた上で、「やりたいならやってみたら?」と送り出したそうです。その子は複数の店舗で働いた後、「お金を稼ぐには効率が悪い」と自分で気づき、自ら辞めていきました。
また、マルチ商法まがいの勧誘販売に引きずられそうな子がいた時も、すぐには止めませんでした。本人の意思を尊重しつつ、職員は裏でクーリングオフ制度を調べたり、本人に誘われたのを機に一緒に店へ行き、職員自身が「私はいらないです」と毅然と断る姿を見せたりしたそうです。
放任ではなく、「見守りとフォロー」がある中で失敗を経験させることで、子ども達が社会に出た後で本当に必要となる力を育てています。
ただ「どこまでやらせてみるか」は職員間でも意見が割れるそうで、職員間でのコミュニケーションが重要だと話してくださいました。
その4. 支援者に最も必要なのは「心のゆとり」
複雑な背景を抱える若者たちと向き合う支援の現場。そこで働く人々には、何が一番求められるのでしょうか。
この問いに対し、講演者さんは「支援する側の心のゆとりと忍耐力」だと断言します。人の支援には「正解」がありません。自分の判断が正しかったのか、もっと良い方法があったのではないかと、誰にも答えを教えてもらえない孤独な葛藤が常にあります。
例えば、腹を立てたある入居者が、職員に向かって「土下座しろ」と要求したときのこと。言われた職員が深く傷ついたのは言うまでもありません。しかし、講演者さんはその時、その言葉の向こう側にあるものに思いを馳せたとお話くださいました。「ああ、この子はこうやって親に言われて育ったんだな。この子はもっと怖くて辛い思いをしてきたのだろう。」
行動の裏にある、本人が受けてきたであろう深い傷や痛みを想像し、受け止めるためにも、「心のゆとり」を持つことが欠かせません。
また講演者さんはこのようにもお話くださいました。
「正解がない支援というのは、結局は自分の子どもたちに対する思いでしか成り立たないなと思っているので、一人一人の子どもを思う気持ちが大事だと感じています。」
講演者さんのホームでは、毎週カウンセラーと職員の会話の機会を設けるなど、支援者側が「心のゆとり」を持ち続けられる仕組み作りにも取組んでいます。
おわりに 「退居してからが本番」
講演者さんはこの仕事を通じ、「世の中で働く人すべてに対して優しい気持ちになれるようになった」とお話くださいました。
ホームの子たちが、様々な困難を抱えながらも、なんとか毎日働きに行っている姿を間近で見ていると、お店で少し不手際な対応をされても、「ああ、この人も一生懸命なんとか働いてるんだな」と感じられるようになったそうです。
自立援助ホームは滞在期間が短いからこそ「退居してからが本番」だと講演者さんは言います。
子ども達にとって、社会で関わる大人の影響は大きいものです。
本人を否定せず温かく関わるボランティアやオンライン里親、失敗しても雇い続ける雇用主など、たくさんの大人のゆるやかで長い支援が必要です。こうした大人の存在が少しずつ若者の生きづらさを解消し、社会で生きる力を作っていきます。
また困難を抱えて頑張る若者は、社会的養護の子だけではありません。
私たちひとり一人が意識して「心のゆとり」をもち、世の中の子すべてを、社会全体で見守りあえる社会になるように、と最後にメッセージをくださいました。
私たちにもできること✨️
以上、自立援助ホーム職員さんの講演より、紹介させていただきました。
自立援助ホームのことだけでなく、支援者として、ひとりの大人として、どうあるべきかという点にも多くの学びや気づきをいただいた講演でした。講演いただいた職員さんに心より感謝申し上げます。
私たちみらいこども財団が支援させていただいている児童養護施設も、入所年齢や期間の違いこそあれ、子ども達にとっては退所後の人生の方が長い点では同様です。
この記事を読んでくださったみなさんとともに、児童養護施設や自立援助ホームの子ども達、また困難を抱えながら頑張る若者たちを見守る社会を作れたらと思います。
みなさんの一歩が、子ども達の支えになるはずです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
自立援助ホームについてもっと知りたい方は、こちらもご覧ください。
✨児童養護施設卒園後の学生を支援するオンライン里親さん募集中!
✨児童養護施設在園中から継続して関わるボランティア募集中!
#みらいこども財団 #児童養護施設 #ボランティア #オンライン里親 #寄付 #社会貢献 #SDGs #里親 #donation #虐待 #貧困 #教育格差 #学習支援
寄付でご支援いただけませんか?
もし私たちの活動にご賛同いただけるなら、自由に使えるお金のうち少しをシェアしていただけませんか?
月100円からはじめられます。
生まれてきてよかったと子どもたちに思ってもらえる未来をつくるため、私たちは決して諦めません。