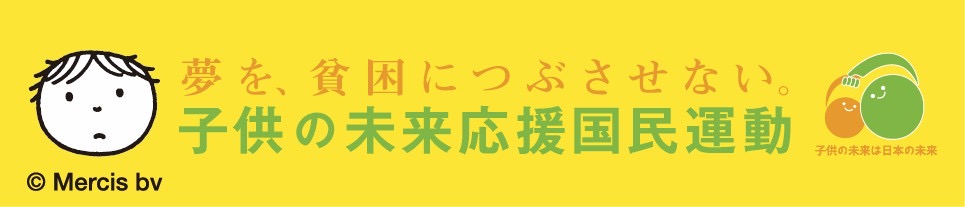みなさんこんにちは!みらいこども財団スタッフの大谷です^^
このシリーズでは毎月1回、社会的養護や児童養護施設について制度や暮らしなどをお伝えしています。
今回も、児童養護施設で日々子ども達を支える、施設職員さんの声をご紹介します。
✨【施設職員さんの声】子どもたちに“普通”の暮らしを届けるために
■ ルールの中で「自由」をどう届けるか
子どもたちと暮らす日々の中で、常に感じるのは、“集団生活のルール”と“個別のニーズ”との狭間です。私たちは、できる限り一人ひとりに合わせた対応を心がけていますが、実際には時間の制約や施設のルールが壁になることも多いです。
「どうして他の子は○○してるのに、私はダメなの?」――そんな声に、何度も悩まされました。中には、「施設だから厳しいんでしょ」「普通の家ではもっと自由なんだよ」というような気持ちを持っている子もいます。
お手伝いを頼めば「やらされてる」と感じてしまい、スマホの制限についても「普通の子はそんなことされてない」と反発されることもあります。子どもたちを守るためのルールなのに、それが子どもたちの“自由”を奪ってしまうように感じられてしまう――このジレンマは、本当に大きいです。
■ 施設職員も“学び”と“余裕”が必要です
職員として働いていて強く感じるのは、制度や法律に対する知識の必要性です。
児童養護施設は、ただ子どもと関わるだけの場所ではありません。運営、制度、法律、経営面……覚えるべきことが本当に多い。でも、PCスキルが不足していたり、制度変更により事務作業が増える中で、結局“子どもと関わる時間”がどんどん削られてしまうというのが現状です。
「本当に必要な時間」はどこにあるんだろう?と、自問することもあります。
■ SNSと“見えない世界”のリスク
いまの子どもたちは、SNSで簡単に“誰とでも”つながれる世界に生きています。
でもそれは、非行や売春、トラブルへの入り口でもあることを、現場で何度も目の当たりにしてきました。表面上は大人しくても、ネットの中で何が起こっているかは私たちには見えません。
「普通の子はやってるから」「友達も使ってるから」――そんな言葉の裏に潜む危険に、どう声をかければいいのか。
“自由”と“管理”の間で、どこまで踏み込んでいいのか、常に悩んでいます。
■ コロナ禍が残した“つながり”の空白
コロナの影響は、子どもたちの日常にたくさんの制限を与えました。
外で遊ぶこと、スポーツ交流、キャンプや遠足――大切な“経験”が、ごっそり抜け落ちたように感じています。行事も制限が多く、「楽しい思い出をつくる」ことができないまま時間だけが過ぎてしまった子もいます。
職員としても、他施設とのつながりを持つ余裕がなくなり、「どうすればもっと良くなるか」を学ぶ機会が減ってしまったのが悔しいです。
ようやく今、少しずつ動き出せるかな…と感じているところです。
■ 少ない人数、重たいケース、そして人手不足
最近特に感じるのが、入所児童数は減っているのに、入ってくる子の背景が重たくなっているということ。
虐待、精神的な問題、発達特性、家庭の崩壊――抱えているものが本当に多い子どもたちばかりです。一方で、職員の数は足りていません。
現場にいると、「これは自分一人では抱えきれない」と思うこともあります。
けれど、それでも毎日顔を合わせる子どもたちにとって、私たちは“唯一の頼れる大人”かもしれない。
だから、踏ん張るしかない。そう思って現場に立ち続けています。
(出典:みらいこども財団実施の全国児童養護施設職員様アンケートより。読みやすいように一部修正を加えております。)
いかがだったでしょうか?アンケートより一部をご紹介しました。
✨私たちにもできること
子ども達を見守る大人の一人になりたいな、と思ったら、近くの児童養護施設に何かできることがないか問合せたり、寄付で応援するのも良いかもしれません。
みらいこども財団でも、交流型奨学金「オンライン里親プロジェクト」や、児童養護施設訪問ボランティアで、多くの優しい大人が子ども達と関わり支える支援を行っています。
みなさんの一歩が子ども達の支えになるはずです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
✨児童養護施設卒園後の学生を支援するオンライン里親さん募集中!
✨児童養護施設在園中から継続して関わるボランティア募集中!
#みらいこども財団 #児童養護施設 #ボランティア #オンライン里親 #寄付 #社会貢献 #児童養護施設ほうもん記 #社員奮闘記 #お礼状 #オンライン
#volunteer #SDGs #里親 #donation #虐待 #貧困 #相対的貧困 #教育格差#学習支援
寄付でご支援いただけませんか?
もし私たちの活動にご賛同いただけるなら、自由に使えるお金のうち少しをシェアしていただけませんか?
月100円からはじめられます。
生まれてきてよかったと子どもたちに思ってもらえる未来をつくるため、私たちは決して諦めません。